とうかぶ2作目(三日御定法編)

歌舞伎 刀剣乱舞 東鑑雪魔縁 (新橋演舞場 2025.7.5〜7.27 予定)
前方で見てたぶん6割くらいしか見えてない2日目と上から見てだいぶ見えた3日目の観劇を踏まえたメモです。まずは、イヤホンガイドなし、筋書読まずで、素で見ました。
初日から3日は三日御定法というそうですが、三日どころじゃなく最後まで刻々と変わるのが新作なので始まりの三日ってことで。
配信も買ったが期限切れまでに全部見られる自信ない。
ネタバレあります、ひきかえせ。(←いつものご注意)
あ、私の歴は、歌舞伎は平成の三之助あたりから。刀剣はとうかぶのみ。なのでゲームの方はわかりません。ごめんください。前作はがっつり見ました。
2年前書いたヤツこちら↓。たぶん新鮮な驚きに溢れてると思います(笑)。今回そこで書いてるようなことは改めて語りません。
へー。ホネホネが敵なんやー、それぞれに曲があるんやー…といったレベルはクリアしたと思ってください。
で、今回の印象ですが、
割と普通の新作になったなと思いました。
急に踊ったり、義太夫が入るタイプじゃないやつです。
古典そのままみたいな所はほぼない。解説もあまり要らないんじゃないか。
しいて言えば新歌舞伎のテイストは少しある。
でもそれはこじつけだな。
「どう見ても歌舞伎だけど見たことない」だった前作から「僕らが歌舞伎と言えば歌舞伎」の方に寄ったかもしれない。
ということはもう、お芝居がどれだけ濃くなるか、どれだけキャラクターが立つかという、普通の問題になってくるので、
月末にどうなっているか、楽しみにします。
道具
盆サイズのなにかを作ってグルグル回しちゃうみたいなのは今回はなし。普通に盆を回して裏面に転換です。
ダイナミックに視点が変わる面白みは減る。割と普通。
大道具としては立ち回りの舞台となる大きな縦長の階段が特徴的です。この幅の道具を高さ方向に長く使うのはあまりないのでは。
でかい階段はそれこそ裸武者の階段落ちのある孤城の落月がありますが
(服着てるだけ膝丸のほうがマシという)
あれはもっと低いような…(うろ覚え。尚、シネマ歌舞伎版には裸武者はないらしい)
こういう、ずどーんと縦に階段が貫いてて、実際に上まで上れるのはなかなか見ない絵です。普通上の方は書割になる気がする。まさに鶴ケ岡八幡宮の場のこの階段ずどーんの浮世絵がありますが、こういう場があったんでしょうかね。
ほか、道具の特徴では、床(地面)が黒いです。
実朝の屋敷では、ごく一部だけ畳を敷き、残りの床の黒い所を余白(余黒?)として残してあります。
上手(右側)に居室があり実朝と妻の倩子姫(せんしひめ)がいる。
この部屋はだいぶパースがついていて面白いです。真四角の部屋を斜めから見たような効果になっています。
その周りの黒いエリアの中に下手(左側)から膝丸が踏み込んでくる。実朝は部屋のいちばん奥から応じている。それが次第に部屋の外に歩み出てくる。心の境界を感じさせます。
やがて運命の日にこの斜めの部屋から真っ黒な外の世界へ実朝は踏み出してゆく。
花道側から見ると今までいた場所がより遠くに見える感じでしょうか。ちょっと違うんだけど、この斜め感には、閉門になった屋敷を後にする大星由良之助的なものも微かに。
雪の時は布を敷いて白になりますが、後の持仏堂の場面でなんか紙吹雪じゃない雪が積もってて、あのフワフワはなんだろう。衣裳に付いても大丈夫なやつだよね。
あと、古典だと高足の床になりそうな座敷でも足がないです。人の座ってる面が低くて近い。
評定の場など、襖の絵がでかいなと感じたんですが物理的に近いからかもしれない。
光、闇
照明は歌舞伎風ではなく客席が暗いです。
歌舞伎だと客席含め全体的に明るく、黒いものは見えないという約束で、見えるけど見えないことにします。
今回のとうかぶでは闇があって、本当に見えないところがあります。スポットライトから外れて光の当たらない真に真っ暗な空間に、気付くと羅刹微塵がいる。上手いことやりますね。
あと、ラスト勢揃いで宗近が出てくるとロイヤルブルーの雪が降るの綺麗だった。
おと
音楽はお芝居のパートは二十五弦箏、十七弦(恐らく)や尺八、琵琶など前作のように色々使われてました。
どこまで録音かは分かりません。
どうやら羅刹微塵の音楽が、前作の禍獣との戦いで使っていたスペイン風のモチーフで
これってそっち側のテーマだったんかと知りました。
かっこいい戦いの音楽かと思ってた。
(あのギターのボディを叩く音みたいなやつも、ハープみたいなやつも、でかい箏でやっています。すごくない?)
黒御簾の下座音楽や長唄はありましたが主役になるのは途中から。
特に、最後のほうの立ち回りではいろんな合方でにぎやかです。
はやがわり
宙乗りや本水のような大がかりな外連(けれん)をやるわけじゃないのは前と一緒
引き抜いたりぶっ返ったりもしてない気がする
(源氏兄弟が肩を脱いで出てくるのはある)
外連は主に、人間が頑張ってます。
これは、とうかぶの特徴だと思うんですが、"早変わりが売りです、いま変わりますよー"的なこれ見よがしな早変わりではなく、別の役者がやってもいいくらいの役をわりとわかんないように変わる。
左近ちゃんの加州清光のスチール写真が出たときネイルをしていたので、あれ、ネイルしてるなら二役はないのかな?と思ったらしっかり二役あって、どうするんだろ?と観てましたら、姫の指、白かったですね。
最近は女形の素足の芸者さんの役で足の爪が刺繍してある靴下を使うらしい。塗るの大変だから。(萬次郎さんの漫画に描いてあったのや。)
じゃあ手もそういうのがあるのかな?。知らんけど。
あと歌昇さんの陸奥守と実朝の早替わりの時に、顔の塗りが茶色っぽいのから白になる。で、また戻る。
これ尋常じゃない早さですよね。
幸四郎さんが去年、やはり同じ幕のうちに白塗りで再登場する早替わりをやってました。
これもびっくりでしたが、今回は白からまた砥の粉に戻ってますからさらにやばい。
歌昇さんのInstagramのリールに実朝の化粧の様子が載っていますが、両手遣いの方なんですね。
あとね、尼御台と雲水の別れの後出てくる小烏丸と同田貫も早い。あれ、そういえばさっきまで出てたふぉぉ、ってなりました。
普通にお芝居を見せないといけない。それを二役をこなす役者がやる。キャラクターの縛りがないイチから作る役。
役者さん達が自らに課した試練みたいにも感じます。
二役の是非についていえば、羅刹微塵は他の人たちに比べて個性があまり効果的に使えているように見えなかった。
もっといけるやろー、まだぶち上がるやろー。
たちまわり
たちまわりは、とんぼとか入ってるけど割合現代風です。人が多いので、乱戦っぽい。伝統的な1対多数の図式もあり、FFXのシーモア戦のような敵側が強くて味方が次々と倒されるのもあり。殺陣師はまつ虫くん、獅一さん。
前のときのどんたっぽの立ち回りを外部の人にお願いするコレじゃない感はなくなった。代わりに見るからに歌舞伎らしいかどうかはわからなくなってきた。(朧を経ての引き出しもあるでしょう。)
まあでも十一段目の立ち回りを生んだ劇団の遺伝子は感じる。
すじとキャラとか
筋書き的には、出陣はあるけど、どのようにその時代の人々に接触しているのかといったことは大胆にカットされており、三日月宗近と鬼丸国綱が最初から普通に尼御台のそばにいるんで、ちょっとびびる。いきなり要件からか。歌舞伎だからいいか。
尼御台の夢に出てくる、錆を拭ってくれってのは、鬼丸自体のエピソードですよね
この流れだとこの翁が悪夢の種みたいに聞こえちゃうのだが。
なんかもう少し、北条への絡みがわかるといいような。
病気の種は羅刹微塵なんですかね、別のものなんだろうか。
民草の怨み、怒りは、源平と北条の時代に日本がどんなドロドロをくぐってきたかを知ってないと伝わらないと思う。ふわっとしてる。
今作では敵が必要だから羅刹微塵を出したという程度にみえるためそちら側のストーリーがわかるといいですね。もし次回があれば。
月蝕の描写も気になる所。若干、朧の森っぽいのも。
刀剣男士については、源氏の兄弟にスポットが当たっているのはありつつ、総花的な感じはします。
元のキャラクターと比して表現の合ってる合ってないについては全くわかりませんが、新しい刀剣男士の印象は、
鬼丸国綱はよくわからないっす。今のところ芝居がほぼアーロン(FFXの)と同じ。
カショーマンの陸奥守は楽しそうでいいですね。
立ち回りも踊りも腰の落とし方がたまらんよね。
加州清光はフォトジェニック。
話し方が独特。歌舞伎でこういう調子で喋る若者はいないんで、類型になくて難しそうだなと思う。
わざわざ地声を選んだんだろうな。
左近ちゃんもう一役の姫は妹背山婦女庭訓の雛鳥、太十の初菊の修行が生きてそうです。(←修正済ここ雛菊て書いてたw 雛鳥と初菊まざってるがな)
やはり実朝と姫、膝丸と実朝辺りの芝居が深くなると面白いと思う。
(ただ、姫が「もしや未来世から…」って言い出すのは、ないわぁ。なぜわかったw)
尼御台と弟の話もあって良さそうなものだけど、あんまり活躍しませんでしたね、義時。
最後に刀が八振り。
前は打ち刀が一つしかなかったからそれだけすぐわかったけど今度はもうわかりません。
てっぺんの三日月と、形でわかる小烏丸だけ。
※(追記)江戸千穐楽にして私気づきました。踊りの最後のフォーメーションの並びや。そういうことか
忠臣蔵の話
ことの当日(とは?)
実朝と姫との別れの後
暗転中に音楽が切れると雪音が鳴って、雪だなってわかる、
歌舞伎の音を解説するときよく出てくる、雪の降る音です。
それから明転して、実朝が出ると、唄と三味線が入って、自分はこの一連に最も歌舞伎を感じました
(※ここが、2日目はこうでしたが、3日目は構成が変わり、暗転の雪音が無くなっていました。初日配信を見返したら、やっぱ雪音はあった。3日目は警備の侍が照明の上がった舞台上でなく暗転中の花道で話しており、その関係かと思います。
この、花道を舞台転換の間に使うのも前作より減ったと思ってましたが後から増える事もあるんですね。もちろん、明転してから雪音自体はあります。階段の場面に来ると音が早くなり、情景の音からやや緊迫感あるBGM性を帯びてきます。)
ビジュアルが発表されたとき、キーは雪だということだけがわかっていた。だから、忠臣蔵を予想した人もいたはず。
その雪だから、が、関係あるのかないのか、本作に忠臣蔵かな?と思われるものが出てきます
姫が尼御台に梅の花籠を持ってきて、鶯が鳴くのを仲章が吉兆だという。
たまたま、バレエのザ・カブキを見たばかりで、顔世御前(塩谷判官の妻)が持っている桜について読んでいたので、花籠の段だ、と思いました。
無論、家つぶれちゃうんで、全然吉兆じゃないんですけど。
あと、付け文との絡みで仲章から義村への忠臣蔵ちっくなパワハラ。
猪武者呼ばわりされてました。
高師直は「なんかムカつく」の総大将みたいなもんですからそれを重ねるの面白いな。
(おじじ、おばばの國矢改め精四郎と蔦之助のコンビが二役で義村、仲章を演じています。)
あと、風雅にふけってる上様に直に詰め寄ってくる若者とその本心を知っている師がいるという図式は御浜御殿を思わせます。
となると、膝丸は富森助右衛門に相当する実直さと熱量で実朝に対峙しなければならない。結構大変。歌昇さん熱いからなー。
膝丸が熟してくればぐっと良くなるはず。
あとは、十一段目の泉水の立ち回り。
雪だし、意識したんじゃないかなあ。
羅刹微塵と鬼丸国綱の太刀合わせは、小林平八郎と竹森喜多八の対決を思わせます。
兎跳び的なあれ(よくコサックダンスとか言われるやつ)もその場面が元ですが、新作では頻繁に入ります。大変なのに入れたくなるやつなのか。
おどり
本編の後に踊りがあります。
大喜利所作事と呼びますが、よくあるのは、この後は大喜利所作事ご覧いただきましょうという口上。私は現実に戻される感じでこれがあまり好きじゃないのです。
今回は現実と作品の狭間にいる押彦、武彦と、歌舞伎本丸の審神者(声:梅玉さん)とのやり取りで、無事任務も終わったし宴だということで世界が続くのが良い。
本編で踊らない代わりに所作事に色々詰めてきました。一曲か二曲なのかと思いきや、結構たくさん。
源氏兄弟が出て、おおさえおおさえよろこびありやーから始まる三番叟。めでたくて良い。他へやらないのはよろこびじゃなくて剣なのね。その後刀尽くしと、髭切膝丸の唄。歌詞読みたいな。
三日月で助六・五郎方面は自分的には意外な組み合わせです。三日月、男伊達のイメージないですもん。
傘の扱いに若干苦戦が感じられる。慣れかな。
獅童と精蔦コンビの三人連獅子もまだ苦戦。
ほかに明らかに毛振り得意そうな人いるのになあ。
あと菊之丞先生が最近よく題材にする那須与一で琵琶と義太夫の掛け合い。三日月、小烏丸。これは二人とも似合ってた。 そのまま踊りの会でやれそう。
浴衣で踊るやつは宴会かな(宴会です)
皆さん達者ですね。歌昇さんがねー。ほらー、いいでしょう?(布教)。大ちゃん(鷹之資)のおてもやんは予想せんかった。
初日配信とちょっとちがうとこ
むつのかみ
みんなが”むつのかみ”を呼ぶイントネーションは初日映像と2日目3日目では変わってました
初日は"若旦那"みたいな下がるイントネーションでした
そこは下げないんだよって何かチェックが入ったのかしら?
それとも歌舞伎では末尾をさげない、の方に従ったのかしら?
膝丸
髭切が団子もって出てきた時弟がいないので
膝丸ーって呼ぶのが、初日はないです。
(御団子食べる兄者かわいいよね)
持仏堂の説明
初日にあった義時と尼御台の侍女たちの花道の場面がカットされましたかね
気のせい?
吾妻鏡
難しい本を持って引っ込む三日月は3日とも違う台詞でした、一回読みかけて「やめておこう」ってやめちゃってた。読もうよw
台詞気になっちゃう、なとこ。
まんまと出てうせた
これは、まんまと〇〇してのけたと言いたかったんかな。出て失せると、居なくなっちゃいますよね。
あらばこそ
あらばだと未然形で仮定じゃない?
あるんだから、あればこそでよくない?
年号
宗近さぁ、てんぽうねんかんって言ってない?だいじょぶ?違う時代に行っちゃわない?

以上、最初のメモでした。
関係ないんだけど、歌舞伎座のアナウンスが若干変わったものになったので、新橋演舞場のお帽子をお取りくださいますよう、花道をお通りになりませんようのアナウンスにはほっとします。これは残して欲しいなあ。
※開演直前アナウンスは今回の歌舞伎本丸の審神者様(梅玉さん)なのでそれではない特別バージョン。退出のときは刀剣男士のローテーション。8振りになったからコンプリートは大変だねー


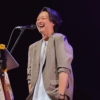









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません